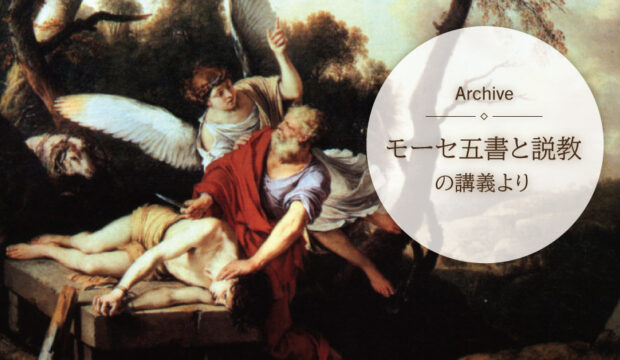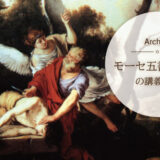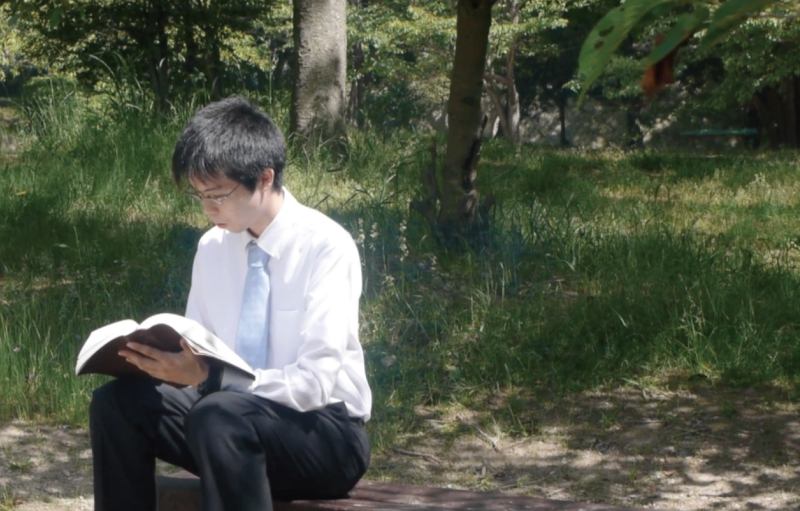教務担当 吉本隆史
はじめに
私たちの信仰生活の指針は、言うまでもなく聖書ですが、教会やキリスト者の過去の歩みから、良くも悪くも多くのことを学ぶことができます。そこでキリスト教会2千年の歴史をわかりやすく簡潔に概観し、みことばの光に照らして今日の教会と信仰者の教訓にしたいと思います。
このシリーズは、本校機関紙「バプテストラッパ」に1998年から2002年に12回にわたり連載した記事を一部書き換えたものです。また邦訳聖書は、『聖書新改訳2017』を使用しています。なお参考文献は最終回に提示させていただく予定です。
教会は聖霊降臨をもって誕生し宣教を続け、広く地中海全域、当時のローマ世界に発展し拡大していきました。しかし同時に使徒の働きにあるような、またはそれ以上の迫害を受けなければなりませんでした。今回は、古代教会の迫害について学びましょう。
Ⅰ.迫害の概要
教会を迫害した最初のローマ皇帝はネロ帝(位54‐68)です。ローマの大火の罪をキリスト教徒に帰し、大迫害を行ったと言われています。ある信者たちは動物の毛皮でくるまれ、縫い付けられて猛犬の前に放り出され、食い殺されました。十字架に付けられた者たち、松脂を塗られ王宮の庭園の松明として燃やされた者たちもいました。ペテロもパウロも、このネロ帝の迫害の時に殉教したと考えられています。
ドミティアヌス帝(位81‐96)の治世下にも迫害があり、使徒ヨハネはパトモス島に流され、そこで黙示録を書きました。さらに続く五賢帝時代(96‐180)にも迫害がありましたが、ここまでの迫害は全体的に見ると地域的で散発的なものでした。
3世紀に入るとローマ帝国は、その衰運を皇帝礼拝の強化によって取り戻そうとしました。そこで皇帝礼拝に抵抗する教会に対して、より大規模で全国的な迫害を行いました。
デキウス帝(位249‐251)は、全属州に対し全面的にキリスト教を禁止し、ローマ国家神の礼拝を強要しました。ローマ監督ファビアヌス(位236‐250)等が殉教しました。
ウァレリアヌス帝(位253‐260)も集会を禁止し教職者を処刑しました。この時にローマ監督シクストゥス(位257‐258)やカルタゴの監督キュプリアヌス(位 ?‐258)等が殉教しました。
またディオクレティアヌス帝(位284‐305)と副帝ガレリウス(位293‐305)の時代には、勅令により、ローマの神々への礼拝、会堂破壊、キリスト教文書の廃棄、信徒の官職剥奪、棄教しない者の投獄、拷問、処刑等が命じられました。迫害は熾烈を極め、多くの殉教者と棄教者が出ました。
Ⅱ.迫害の原因
帝国は始め、キリスト教を公認宗教であるユダヤ教の一派と見ていました。しかしユダヤ教と区別されるようになり、非公認宗教つまり非合法宗教とされ、帝国の安全を脅かすものとされてしまいました。
皇帝の神の祭壇に犠牲をささげれば、個人的な宗教を信奉することができました。国家の安定に貢献するなら個人の宗教は許容されました。これは今日の日本も同じです。家の宗教を信じなくても維持するなら、個人の信仰は許容され反対を受けません。しかしキリストに忠実に従おうとするなら、どうしても反対や摩擦が起るのです。
さらにキリスト教への誤解や、キリスト教により利益を失う宗教者や偶像製作者の怒りも迫害の原因でした。また異教的な行事や不道徳から遠ざかることで、社会の不興を招くこともありました。
このような迫害の原因はすでに聖書に記されており、また私たちが身近に体験するものと根本的に同じであることがわかります。キリスト者は世のものでないので、世がキリスト憎んだようにキリスト者を憎みます(ヨハ17:14)。また世は自分の利益が脅かされると迫害します(使19:23‐40)。さらに罪から離れた生活をしようとすると世の不興を買うようになります(Ⅰペテ4:2‐5)。「キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受けます。」(Ⅱテモテ3:12)と書かれている通りです。
Ⅲ.迫害の結果
迫害によりキリスト者は財産や社会的立場を失うなど、多くの犠牲を払いました。教会は多くの投獄者や殉教者を出しました。またキリスト者の中には、迫害のために妥協する者や信仰を捨てる者もありました。その他、迫害は様々な困難や問題を教会にもたらしました。しかし不思議なことにキリスト教は拡大していったのです。
また激しい迫害の中、教会は生命を賭しても守るべき文書と生命のためには放棄してよい文書を、研ぎ澄まされた霊的洞察で区別するように聖霊によって導かれました。このようにして神の摂理のうちに内在する権威を持つ新約聖書正典が確認されていったのです。
さらに迫害によって教会が主に聖別されるように導かれました。4世紀になりキリスト教が容認され、さらに国教化され、権力を獲得するようになると、霊的には堕落し少しずつ真理から離れていくことになりました。迫害はキリスト者の信仰を純粋なものとし、その歩みをきよめる役割を果たしていたのです。
このように大きな試練の中にも、主の御手がありました。今日の日本に住む私たちも、当時のような迫害はなくても、世との摩擦や日常生活の中で試練があるかもしれません。しかしその中でも神は共におられ、愛と摂理をもって私たちを守り導いて下さっているのです(マタ10:28‐31)。
155‐156年に、小アジアのフリュギアで迫害がありました。その迫害時にスミルナ(現トルコ共和国のイズミール)で50年以上監督であったポリュカルポス(70頃‐155)は捕えられ、競技場に集まった群衆の前で地方総督の審問を受けました。
総督は老齢のポリュカルポスに、「いい年をして、少し自分を大事にしたらどうだ。…皇帝陛下の守護神にかけて誓うがよい。…誓ったら釈放してやろう。そしてキリストを誹るがよい」と言いました。ポリュカルポスは答えました。「私は86年間もキリスト様にお仕えして参ったが、ただの一度たりとも、キリスト様は私に対して不正を加え給うようなことはなさらなかった。どうして私が、私を救い給うた私の王を冒瀆するようなことができようか。」
私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。
(テモテへの手紙 第二 2章13節)
さらに総督が「火で焼くこともできるのだぞ。」と脅すと、「貴下は、ほんの一時燃えてじきに消える火などを持ちだして私をおどかしたつもりになっておられるが、来るべき未来の審判の火をご存知ないのであろうな。その火は信仰心のない者には永遠の懲罰を与える火なのだ。」と返し、火刑に処せられました。
からだを殺しても、たましいを殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ、たましいもからだもゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。
(マタイの福音書 10章28節)
キリスト者は「生ける望み」を持ち、「朽ちることも、汚れることも、消えて行くこともない資産を受け継ぐように」されました(Ⅰペテ1:3‐5)。ですから試練の悲しみの中にも喜びを持つことができます(同1:6‐9)。十字架の道に歩まれた主(同2:21‐25)と、迫害の中でも望みに生きた聖徒たちにならい、生涯、忠実に主に従っていきたいと思います。
「死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与える。」
(ヨハネの黙示録 2章10節)